故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る
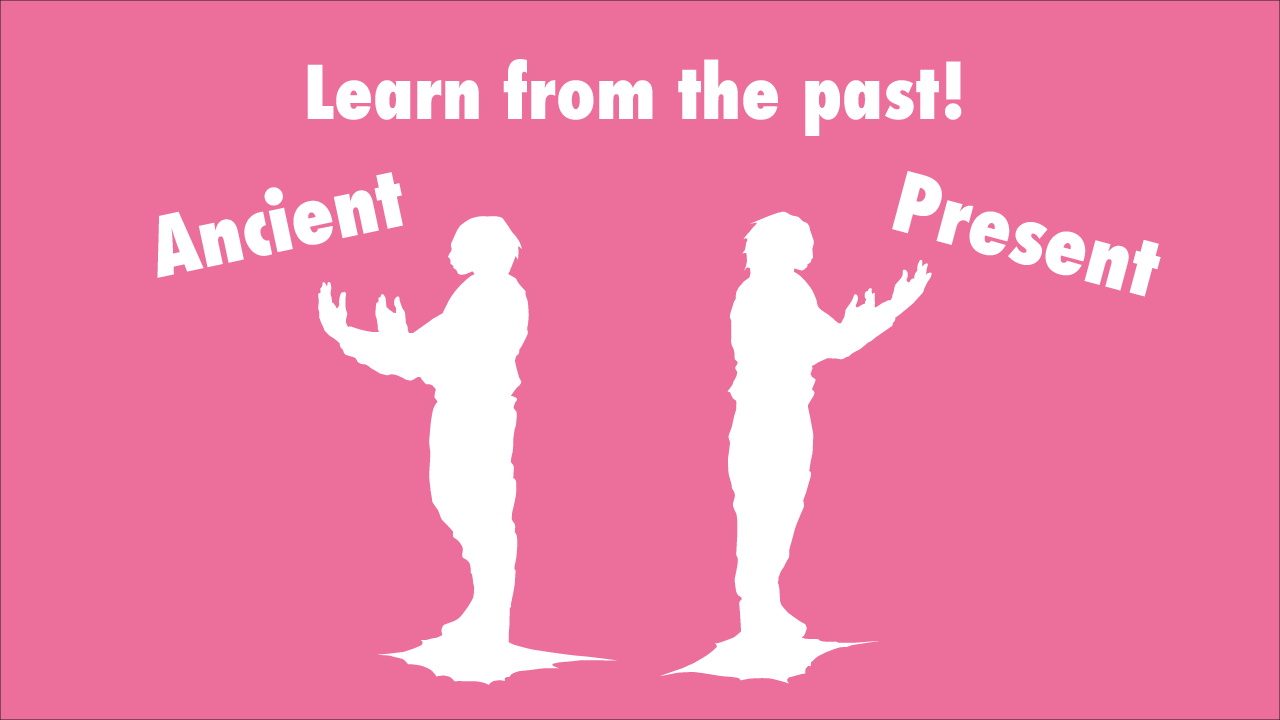
今回は「温故知新」というテーマで、何か新しいものだけでなく、これまで私たちが培ってきたものについて再考してみようと思う。
明治になり、それまで鎖国していた日本に西洋の文化、文明がどっと流れ込んできた。 ー散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする。ー その時に、今まであった日本古来の文化を捨て、新しく西洋の文化を取り入れるということが多くあった。 しかしその時に、捨てなくては良いもの、日本の良さというものもあったのではないか? それは思想や考え方というようなものでも同じだ。 確かに江戸時代までは、鎖国していたことや「井の中の蛙」状態ということもあっただろう。しかしそんな中からユニークな文化が生まれるということもあったのではないか?浮世絵など、海外でも高い評価を得たものもある。 今はグローバル社会になっているが、絶えず世界の動向を注意していく、世界標準でものを考えていくということが大切だとはよくいわれるが、何か海外のもので、よいところは取り入れつつも、日本のよさも忘れてはいけないなと思う。 それでは、日本の良さとは、いったいぜんたいなんだろう?例えば、海外の文化を日本風にアレンジして楽しんでしまう、ということは得意なのではないか?ハロウィン然り、クリスマス然り。。 また、例えば、文字がそうだ。もとは中国から伝わった漢字がやがて平安時代に日本特有の平仮名、カタカナとなっていった。 また、奈良時代や平安時代には、大陸から伝わった仏教などを日本風にアレンジして取り入れてきた。 そして料理などもそうだ。カレーなど外国から伝わった料理などを日本風にアレンジして楽しんでいる。 貿易でも海外から資源を輸入して日本で加工し海外へ輸出するということは以前から日本を支えてきたビジネスモデルだ。
上記のような「外国からのものを日本で加工、アレンジして新しいものを作る」というところが日本の得意分野で「強み」なのではないか? そして、話は少し変わるが、新しいものだけに何か価値があるのではないことも、普段生活している中で気付くこともあるはずだ。本を読むにしても、古典といわれるようなものは何百年も前に書かれたのに、今も人々の心を打つ。 新しいことを取り入れつつも、これまで自分たちが培ってきたものも忘れてはならない。 昨今はIT技術やAIの進歩が激しい。しかしこれまで私たちが培ってきたものがあるからこそ、それらのテクノロジーが生きるのである。 自分のことを書くと、、遊びに遊んだ学生時代、そして今は仕事一辺倒で、しかし何か限界のようなものを感じている。だが、ここで学生時代の何か遊びに遊んでいた頃を思い出して、そしてそれを今取り組んでいることとミックスしてみたら何か気づくこともあるかもしれない。。。 温故知新で頑張っていきましょう! 以上

