成熟社会を楽しもう!
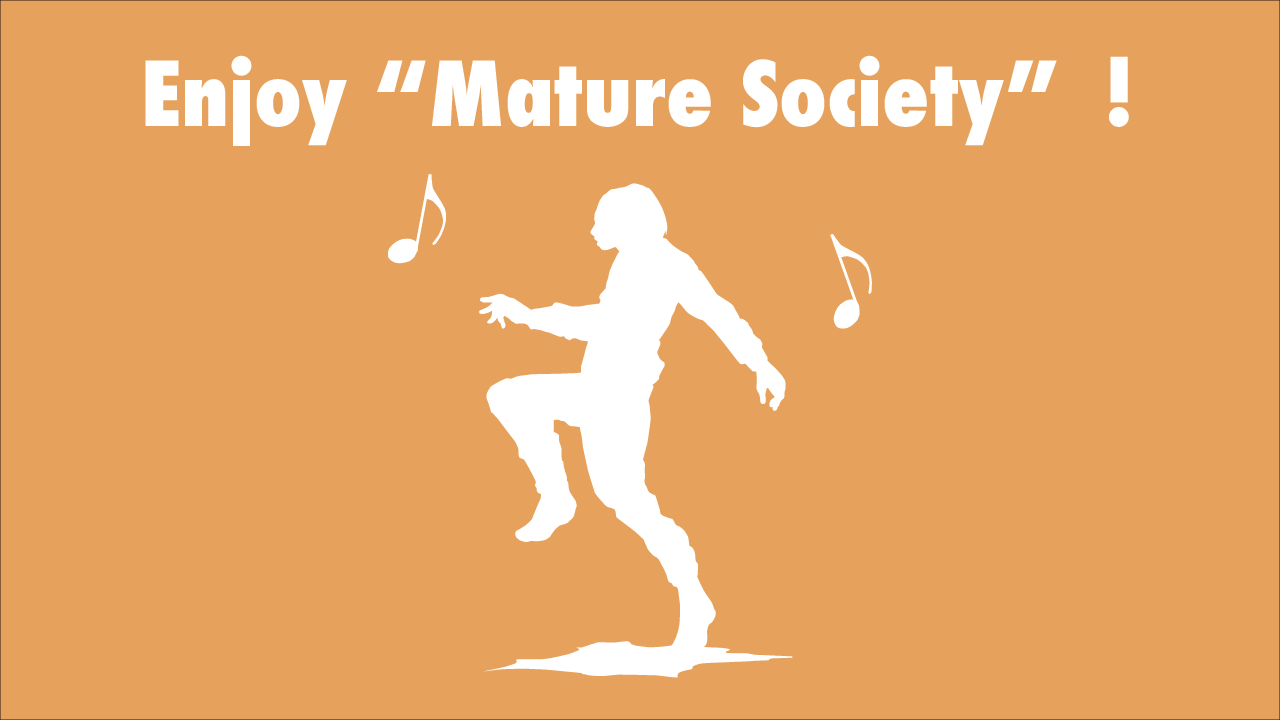
藤原和博さんの著書『35歳の教科書』(ちくま文庫)を以前読ませていただいたのですが、成熟社会には成熟社会の「考え方」というものがあると書かれていました。以前の投稿でも書きましたが、「アール・ド・ヴィーヴィル」というものらしいのですが、成熟社会を生きるフランス人の生活信条で自分らしい豊かな生き方、暮らしの美学だそうです。例として、その箇所を引用いたしますと、
「それはたとえば人に道を譲りながら、服装や髪型を褒めることかもしれません。料理のためにテーブルクロスを選ぶようなことであり、パートナーのためにとっておきのワインを抜く瞬間だったり、電車を一本遅らせて次の電車に座っていくことだと語る人もいる。」 ということだそうです。 はっきりといた定義はないそうなのですが、それは誰かと会うときに、より楽しくなる工夫というようなことや、何かちょっとした楽しくなるような、楽しめるようなアイデアだとか仕組みだと思います。 また、何かを楽しむという文脈で、リテラシーについても書かれていまいたが、リテラシーを身につけることによって、より良く生きるということはもちろんなのですが、そのことによって生活がより「楽しくなる」、また「楽しめる」のではないでしょうか。 リテラシー(literacy) 1 読み書き能力。また、与えられた材料から必要な情報を引き出し、活用する能力。応用力。2 特定の分野に関する知識や、活用する能力。「コンピューターリテラシー」「情報リテラシー」 (コトバンクより) 例えば読み書き能力を身につけることによって、本を読むことができたり、何か手紙やメッセージで誰かに自分の思いを伝えたりできます。そのことによって生活がより良くなり、ひいては生活が楽しくなるのではないでしょうか。 また、PISA型試験で問われているリテラシーについても同じように、それらを身につけることによって生活がより良くなり、楽しくなるのではないかと思います。 ⚫︎数学的リテラシー
数学的リテラシーとは、「数学が世界で果たす役割を見つけ、理解し、現在及び将来の個人の生活、職業生活、友人や家族や親族との社会生活、建設的で関心を持った思慮深い市民としての生活において確実な数学的根拠にもとづき判断を行い、数学に携わる能力」である。 数学的リテラシーは数学を学ぶことによって、世の中や自分の普段の生活を数学を使って考えることができ、結果として生活をよりよく、そして楽しむことができる、と言えるでしょう。 ⚫︎科学的リテラシー
科学的リテラシーとは、「自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化について理解し、意思決定するために、科学的知識を使用し、課題を明確にし、証拠に基づく結論を導き出す能力」である。 同じく科学リテラシーを身につけることによって、科学の理論などがわかり、例えば自然現象や製品などにどんな科学的な理論や法則、仕組みが利用されていることを理解できるし、それがひいてはより生活を楽しむことにつながるのでしょう。もちろんさまざまな課題に対しても、その解決のために科学的知識、リテラシーが役に立つのは言うまでもありません。
「⚫︎⚫︎リテラシー」という言葉は最近よく耳にします。先ほどの繰り返しになりますが、リテラシーを身につけることによって、より良く生きるということはもちろんなのですが、そのことによって生活がより「楽しくなる」、そしてより「楽しめる」のではないでしょうか。 成熟社会とは以前とは違い「もの」を買ったり消費したりということが豊かさには直結しなくなったものの、何かを楽しむ、ということが一つ、成熟社会の豊かさなのではないでしょうか。これが豊かさだというはっきりとした基準はないものの、いかに楽しむために工夫するか、と言うのも何か楽しいですよね。 例えば、推し活なんてものも、楽しむための仕組みだと思います。 Enjoy!
楽しもう!!

